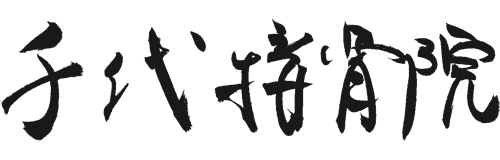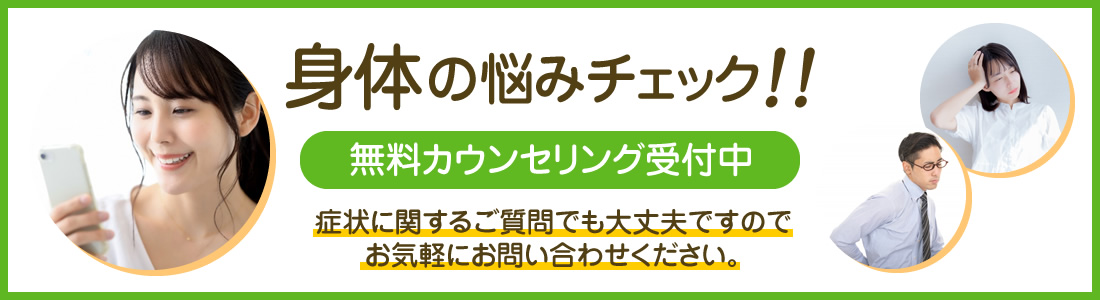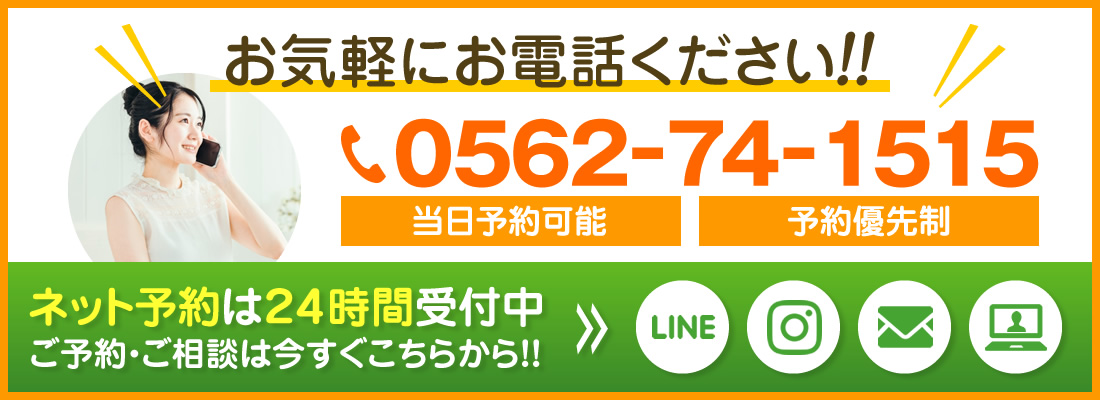しつこい痛みが続く四十肩、五十肩の痛みの原因と治療方法
このようなお悩みはありませんか?
- 肩が痛くて眠れない
- 髪を洗うときに肩に痛みがある
- ズキズキ、ウズウズする肩の痛みがある
- 肩が動かしにくい
- 四十肩・五十肩がなかなか治らない
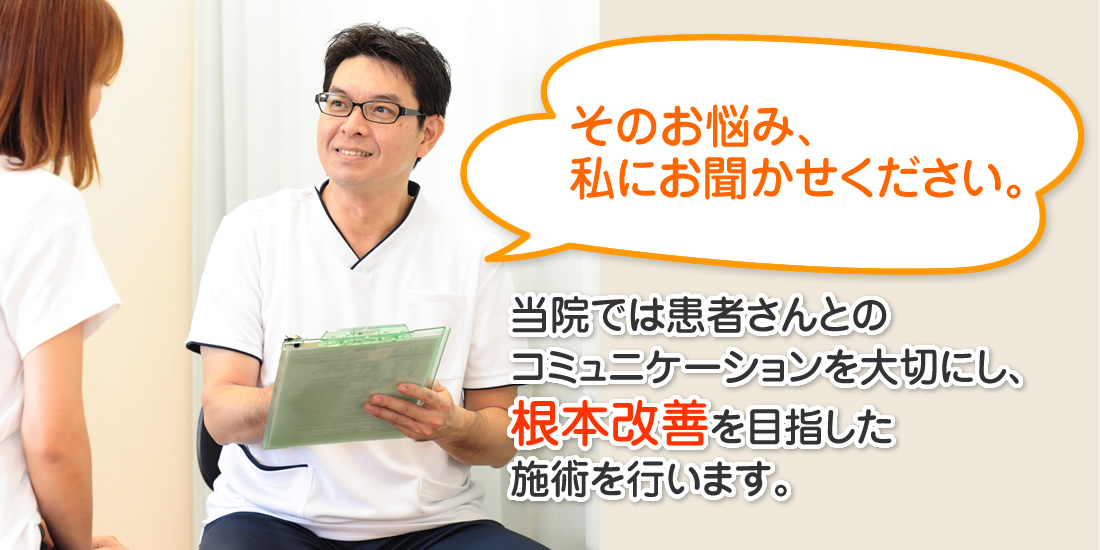
四十肩、五十肩とは?
四十、五十肩は関節痛の一種で、年齢を重ねると、肩の関節がスムーズに動かなくなることがあります。このような症状を、通称「四十肩」「五十肩」と呼びます。
「四十肩」「五十肩」は医学的には「肩関節周囲炎」と診断され、肩関節周囲の筋肉や関節に炎症が起きている状態のことです。四十肩、五十肩は、その名の通り40代で症状が出れば四十肩、50代で症状が出れば五十肩と呼んでおり、それぞれに症状の違いはありません。
四十肩・五十肩は加齢によるものが多く、特徴としては、肩を上げたり、腕を後ろに回したり、水平に保とうとすると肩関節周囲に鋭い痛みがあります。
そのため、日常生活では、
- 洗濯物が干しづらくなる
- 肩よりも上のものが取りづらくなる
- 背中のファスナーが上げられない
- 入浴時に背中を洗えない
などの症状が現れます。
よく肩こりと混同されてしまいがちですが、肩こりは筋肉の緊張などから起こるもので、四十肩、五十肩とは病態が異なります。肩こりとの見極め方は、「肩が動かせるかどうか」です。肩こりの場合は動かせますが、四十肩・五十肩の場合は動かせなくなります。
四十肩、五十肩の原因

四十肩、五十肩は、肩関節周囲に付く、細かい筋肉(腱板あるいはローテーターカフと呼ばれます)の加齢による摩耗によって炎症を起こし、痛みが出ます。加齢に伴うものであること以外、はっきりとした原因は分かっていないとされています。
よって日常生活や仕事で肩関節をよく使う方、筋肉の柔軟性が低下しやすい運動不足の方に起こりやすいとされています。
四十肩・五十肩の症状
肩を動かすときに鋭い痛みが出るのが特徴です。ピーク時には「夜間痛」といって、夜眠れないほどの激痛に襲われることもあります。こうなると日中、何もしなくても痛みがあり、痛みの範囲も肩全体から腕までと広範囲に及びます。
- 髪を後ろに束ねる
- 電車でつり革を掴む
- 服を着替える
- 洗濯物を干す
- エプロンの紐を結ぶ
- シャンプーをする
- 歯を磨く
- 身体を洗う
などの動作の際に痛みを訴える方が多いです。これらは日常生活で行う動作であるため、生活が不便に感じるようになります。
四十肩・五十肩の進行
四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)は以下のように4つの段階を経て症状が進行します。期間は人によってそれぞれなので、あくまで目安になります。
①発症期(数週間~数カ月)
きっかけがなく痛み始め、発症の時期を特定できないケースがほとんどです。特定の場所に炎症が起こり、いつの間にか痛みがじわじわと強まっていきます。
②炎症期(10日~2週間)
炎症がピークの状態です。肩や腕を動かすと激痛が走り、何もしなくても痛みがあります。この時期は、痛みが強すぎてその範囲を特定できません。「夜間痛(眠る時間帯の痛み)」により、睡眠障害になる人もいます。 痛みを我慢して慢性化させてしまうと、回復にも時間がかかってしまうことがあります。
③回復期(約1カ月)
痛みが和らぎ、痛みの範囲も肩の前面や側面など「ここが痛い」と特定できるようになります。この段階で油断すると、「②炎症期」に逆戻りすることもありえます。②と③を長期間繰り返す人もいるので注意が必要です。
④炎症完全沈静期(約1カ月)
痛みが消えていく期間です。ただ、肩関節まわりの筋肉や滑膜と呼ばれる関節内を覆う組織が炎症の影響で固まっているため、肩の動かしにくさが残ります。(関節可動域制限)
四十肩・五十肩の治療・対処法
四十肩 五十肩の治療は上記の進行度合いに応じて違います。 まずは 症状がどの段階にあるか特定することが非常に重要です。
痛みが強い時期は無理に動かさない
①、②の発症期や炎症期はとにかく炎症を強くしないことが非常に重要です。痛みを誘発するような肢位を取ったり、 肩関節を無理に動かすような運動をすると炎症が強くなり、その後の回復過程に余計に時間がかかってしまうことになります。 痛みは体からの危険信号のサインです。
四十肩・五十肩は痛みが出てきたら、まずはその痛みをできるだけ誘発しないようにして日常生活を過ごすことが重要になります。 また、炎症が特に強い時期は内服の痛み止めやアイシング( 冷やす) を効果的に使い、 適度に痛みや炎症を抑えることも重要です。特に夜間痛が強く、眠れなくなると二次障害が発生し、生活全般に悪影響が出ます。痛みのため眠れない要な場合は薬や痛み止めを検討しましょう。
痛みがなくなったら徐々に肩を動かす
その後、炎症と痛みが回復し、回復期になってきたら、 痛みが出ない範囲で徐々に肩を動かすことを意識していきます。
④の炎症完全沈静期後は、しばらく肩関節を動かせなかったため、肩関節の拘縮が起きています。 拘縮とは、筋肉や関節がこわばって固まってしまい、関節の動かせる範囲が狭くなってしまうことです。 主に怪我や不動(長期間動かさないこと)によって拘縮が発生します。肩関節周囲炎は英語では FrozenShoulder(フローズンショルダー:凍結した肩)と呼ばれるほど拘縮が発生しやすい疾患です 。
痛みがなくなってきた時期から徐々に肩関節の動かせる範囲を広げていくことで、以前のように肩を自由に動かすことができるようになります。
しつこい痛みが続く四十肩・五十肩の施術
当院では、首から足首の関節の調整など、痛みのない施術方法で全身の歪みを整えることで、今までマッサージだけでは改善されなかった症状に対して根本改善を目指した施術を行っていきます。
人間の背骨には交感神経・副交感神経が通っています。背骨の歪みにより、交感神経や副交感神経のバランスが悪くなり自律神経の乱れが生じます。
背骨や骨盤の歪みを中心に関節を整えることで自律神経のバランスを整え、安定させます。また日常生活や食事におけるアドバイスをすることで根本的な改善を目指します。
どんな症状も、生活習慣の改善(規則正しい生活リズム、適度な運動習慣の確立、自分に合ったストレス解消法を見つけることなど)と食事の栄養バランスを整えることはとても重要なファクターで、根本的な治療を行っていくためには欠かせません。
私共は患者様とのコミュニケーションを第一に考えています。一緒に相談しながら改善していきましょう!